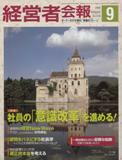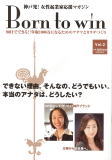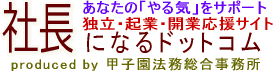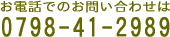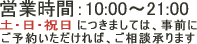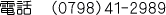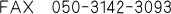現在(2023年9月末まで)の消費税納付の仕組み
原則として、
【売り上げと一緒に受け取った消費税】−【仕入や経費支払と一緒に支払った消費税】=税務署に納付する消費税
となります。
![]()
消費税が課税される売上が5000万円を超えない事業者の場合は届け出をすれば「簡易課税制度」にて納税できます。
![]()
消費税が課税される売上が1000万円を超えない事業者の場合は消費税納付の義務が免除されます。(免税義務を放棄して消費税を納付することも可能)
A会社(商品を製造)
B会社(卸売。Aより商品を買い付け)
C会社(小売。一般消費者に販売)
D消費者
として、消費税の流れを見ていくと、
- A会社が商品を製造。製造した商品を5万円(税抜)でB会社に販売
- →A会社は55000円をB会社より受け取り、消費税5000円を税務署に納付
- B会社が商品を卸売。仕入れた商品を7万円(税抜)でC会社に販売
- →B会社は77000円をC会社より受け取り、消費税2000円(7000−5000円)を税務署に納付
- C会社が商品を店頭販売。仕入れた商品を10万円(税抜)でD消費者に販売
- →C会社は110000円をD消費者より受け取り、消費税3000円(10000−7000円)を税務署に納付
- D消費者は商品購入の際にC会社に110000円(消費税1万円)を支払う。
以上より、D消費者が支払った消費税10000円は、
A会社が5000円、B会社が2000円、C会社が3000円
と分担して税務署に納付したことになる。
これが消費税の納付の仕組みです。
ところが、B会社が売上1000万円以下の免税事業者だとすると、
- A会社が商品を製造。製造した商品を5万円(税抜)でB会社に販売
- →A会社は55000円をB会社より受け取り、消費税5000円を税務署に納付
- B会社が商品を卸売。仕入れた商品を7万円(税抜)でC会社に販売
- →B会社は77000円をC会社より受け取る。B会社は消費税免税事業者なので、消費税2000円(7000−5000円)を税務署に納付しなくていい。
- C会社が商品を店頭販売。仕入れた商品を10万円(税抜)でD消費者に販売
- →C会社は110000円をD消費者より受け取り、消費税3000円(10000−7000円)を税務署に納付
- D消費者は商品購入の際にC会社に110000円(消費税1万円)を支払う。
以上より、D消費者が支払った消費税10000円は、
A会社が5000円、B会社が0円、C会社が3000円
と8000円しか税務署に納付されないことになる。
これでは消費者が損をしているということで、
C会社(免税事業者)が納めるべき消費税をなんとかして徴収できないか?
と考え出された方法が、2023年10月1日から始まる適格請求書等保存方式(一般的に「インボイス制度」と呼ばれている)です。
2023年10月1日以降の消費税納付の仕組み
この制度が始まると、消費税納付の仕組みは下記のようになります。
![]()
【売り上げと一緒に受け取った消費税】−【仕入や経費支払などでインボイス制度に登録した課税事業者に支払った消費税】=税務署に納付する消費税
![]()
消費税が課税される売上が5000万円を超えない事業者の場合は届け出をすれば「簡易課税制度」にて納税できます。
![]()
消費税が課税される売上が1000万円を超えない事業者の場合は消費税納付の義務が免除されます。(免税義務を放棄して消費税を納付することも可能)
先に記載したA〜Dの例えで説明すると、
A会社・B会社・C会社がすべて消費税課税事業者であれば、
- > A会社が商品を製造。製造した商品を5万円(税抜)でB会社に販売
- > →A会社は55000円をB会社より受け取り、消費税5000円を税務署に納付
- > B会社が商品を卸売。仕入れた商品を7万円(税抜)でC会社に販売
- > →B会社は77000円をC会社より受け取り、消費税2000円(7000−5000円)を税務署に納付
- > C会社が商品を店頭販売。仕入れた商品を10万円(税抜)でD消費者に販売
- > →C会社は110000円をD消費者より受け取り、消費税3000円(10000−7000円)を税務署に納付
- > D消費者は商品購入の際にC会社に110000円(消費税1万円)を支払う。
> 以上より、D消費者が支払った消費税10000円は、
> A会社が5000円、B会社が2000円、C会社が3000円
> と分担して税務署に納付したことになる。
![]()
となり、インボイス制度が始まる前と全く変わらないことになります。
大きく変わるのは免税事業者が加わったときです。
B会社が売上1000万円以下の免税事業者だとすると、
- A会社が商品を製造。製造した商品を5万円(税抜)でB会社に販売
- →A会社は55000円をB会社より受け取り、消費税5000円を税務署に納付
- B会社が商品を卸売。仕入れた商品を7万円(税抜)でC会社に販売
- →B会社は77000円をC会社より受け取る。B会社は消費税免税事業者なので、消費税2000円(7000−5000円)を税務署に納付しなくていい。
- C会社が商品を店頭販売。仕入れた商品を10万円(税抜)でD消費者に販売
- →C会社は110000円をD消費者より受け取る。B会社はインボイス制度に登録していない事業者なのでD消費者から受け取った消費税10000円(10000−0円)を税務署に納付
- D消費者は商品購入の際にC会社に110000円(消費税1万円)を支払う。
以上より、D消費者が支払った消費税10000円は、
A会社が5000円、B会社が0円、C会社が10000円
と15000円が税務署に納付されることになる。
(国は予想外に納税されることになり喜ぶ)
困るのは消費税納税額が大きく増えるC会社で、
「インボイス制度に登録していない免税事業者から仕入購入すると損するから、インボイス制度に登録している課税事業者から仕入購入しよう」
と考えるはずです。
![]()
よって、先に記載したような「国が喜ぶような状態」は長続きせず、
A会社・B会社・C会社がすべて消費税課税事業者となり、
- A会社が商品を製造。製造した商品を5万円(税抜)でB会社に販売
- →A会社は55000円をB会社より受け取り、消費税5000円を税務署に納付
- B会社が商品を卸売。仕入れた商品を7万円(税抜)でC会社に販売
- →B会社は77000円をC会社より受け取り、消費税2000円(7000−5000円)を税務署に納付
- C会社が商品を店頭販売。仕入れた商品を10万円(税抜)でD消費者に販売
- →C会社は110000円をD消費者より受け取り、消費税3000円(10000−7000円)を税務署に納付
- D消費者は商品購入の際にC会社に110000円(消費税1万円)を支払う。
以上より、D消費者が支払った消費税10000円は、
A会社が5000円、B会社が2000円、C会社が3000円
と分担して税務署に納付したことになる。
![]()
というように適正な消費税額が納付されるようになる、となるはず。
これがインボイス制度導入の仕組みです。
国にとっては「適正に徴収できる」か「たくさん徴収できる」かのどちらかにしかならず、制度導入しても損することがありません。
困るのはインボイス制度に登録していないB会社です。
「B会社から購入すると納付する消費税額が増えるから、やめておこう」
となり、免税事業者のままでいるとおそらく倒産してしまいます。
このインボイス制度は欧米ではすでに導入済みです(消費税制度がある先進国で導入していないのは日本のみ)。
インボイス制度を導入した国では、免税事業者は淘汰され特殊な産業以外残っていません。
よって「B会社」のような会社は制度導入後数年で消えてなくなることになります。
ただ、販売先がC会社のような「一般消費者ばかり」であれば、免税事業者として生き残ることは可能です。(欧米で生き残っている「特殊な産業」に該当します)
- A会社が商品を製造。製造した商品を5万円(税抜)でB会社に販売
- →A会社は55000円をB会社より受け取り、消費税5000円を税務署に納付
- B会社が商品を卸売。仕入れた商品を7万円(税抜)でC会社に販売
- →B会社は77000円をC会社より受け取り、消費税2000円(7000−5000円)を税務署に納付
- C会社が商品を店頭販売。仕入れた商品を10万円(税抜)でD消費者に販売
- →C会社は110000円をD消費者より受け取ったが免税事業者なので、消費税3000円(10000−7000円)を税務署に納付しない
- D消費者は商品購入の際にC会社に110000円(消費税1万円)を支払う。
以上より、D消費者が支払った消費税1万円は、
A会社が5000円、B会社が2000円、C会社が0円
と7000円しか税務署に納付されないことになる。
![]()
C会社のお客は一般消費者が圧倒的多数を占め、消費税の納付計算なんて関係がないので、おそらくお客はほとんど離れない。
ではどのような産業がこのC会社に該当するのか考えていくと、
「通常の事業の経費にならないもの・サービスを扱っている」
とか、
「事業の経費にはなるが、金額が小さく頻度も低いものやサービス」
となる。
- 「通常の事業では経費にならないもの・サービスを扱っている」
- →理美容業やエステ、学習塾、趣味の習い事教室、おもちゃ屋、ペットショップ、お墓参り代行業など
- 「事業の経費にはなるが、金額が小さく頻度も低いものやサービス」
- →駄菓子屋や縁日の屋台、自転車の修理屋さんなど
この文章を書いていて思いついたのが上記のお店。
探せばもっとあるはず。
なお、インボイス制度が2023年10月1日に始まっても、いきなり、
「全く免税事業者から購入した際に支払った消費税を差し引けない」
というわけではなく、猶予期間が設けられています。
- 令和8年9月30日(制度運用開始から3年間)までは、免税事業者に支払った消費税額の80パーセントを、納税額算出の時に控除できます。
- 令和8年10月1日以降は、令和11年9月30日まで、免税事業者に支払った消費税額の50パーセントを、納税額算出の時に控除できます。
- 令和11年10月1日より、免税事業者に対する控除が認められなくなります。
インボイス制度への登録の仕方
2つの要件を満たす必要があります。
| 【要件1】 消費税課税事業者であること。 |
| 免税事業者がインボイス制度に登録するには「免税義務を放棄して、消費税課税事業者になります」という登録をしなければいけません。 ※ただし、2023年10月1日の制度開始日からインボイス制度に登録したい場合は、2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、2023年10月1日から自動的に課税事業者になります。 |
| 【要件2】 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出すること。 |
| 2023年10月1日の制度開始日からインボイス制度に登録したい場合は、2023年3月31日までに書類提出する必要があります。 |
制度の開始が10月1日なので、個人事業の免税事業者の中には、
「3ヶ月だけのために消費税申告書を作るのは面倒なので、2023年10月〜12月の売り上げをなるべく少なくして、2024年1月からインボイス制度に登録しよう」
と考える人も結構いると思われます。
この場合は、
「課税事業者になる課税期間の初日の前日の1ヶ月前までに登録手続を行うこと」
となっているので、2023年11月30日までに、
・「消費税課税事業者になる届け出」
・「適格請求書発行事業者の登録申請書」
の2つを行うことになります。
次のページは、
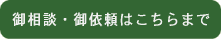
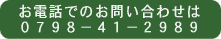
・会社設立費用・価格表
・会社設立依頼はこちら
・会社設立無料相談はこちら
・依頼に関するQ&A
・会社用印鑑販売
・会社についての基礎知識
・会社の種類
・会社設立のメリット
・会社設立のデメリット
・株式会社のメリット・デメリット
・合同会社のメリット・デメリット
・会社設立Q&A
・NPO法人で起業・独立する際のメリット・デメリット
・NPO法人の利用方法
・NPO法人の作り方
・NPO法人何でもQ&A
行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

詳細プロフィールはこちら